菊地 悦子(きくちえつこ)
【からむしとブー】
先日、昭和村公民館で、昭和村のからむしをテーマにした映画「からむしのこえ」と、沖縄県宮古島のブーを描いた「ブーンミの島」の2本が同日上映された。それぞれの映画はすでに何度か上映されていて、わたし自身も別々には観ているのだけれど、両作品を観比べたくなり、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館まで出向いて視聴してこようかと思っていた矢先、昭和村での上映会を知ったのだった。
イラクサ科の多年草である苧麻(ちょま)を、昭和村ではからむしといい、宮古島ではブーと呼ぶ。縄文の世から縄や衣服に利用されてきた植物だ。かつては日本の各地で栽培されていたが、木綿の登場や養蚕の盛況、化学繊維の普及、そして和装の機会の減少などにより、全国から苧麻文化の多くが失われ、今では昭和村と宮古島にその伝統的な技術が残されるのみになった。
2012年から数年間、宮古島に暮らした。そのきっかけのひとつが、宮古の織物文化をテーマにした事業のお手伝いで、そのとき初めて宮古島と昭和村が同じ植物で繋がっていることを知った。織手さんの家に苧麻文化の交流を謳った古いポスターが貼られていて、その会場が昭和村だったのだ。
サンゴ礁の海に囲まれた南の島と、東北の山間の雪深い村。植生も人の歴史も暮らしもまるで違うはずの宮古島と昭和村で、育まれ受け継がれてきたからむしとブー。遠く離れたふたつの場所に通底するものは何なのか、わたしはひどく興味をもった。
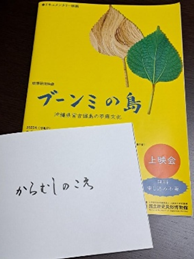
撮影、録音:春日 聡、分藤大翼/『ブーンミの島』時間:113分 制作年:2022年 監督:春日 聡
【からむしだけはなくすなよ、という祈り】
映画「からむしのこえ」の中で、村の人たちは声をそろえていう。「からむしだけはなくすなよといわれてきた」のだと。だけは、という言葉は強い。そこには外部の介入や時代のいかなる変化の中にあっても、「なんでかんで守んなんね」という使命と覚悟があり、その言葉のとおり、村人たちはからむしの一年と丁寧に向き合う。
映画は、長い冬がようやく明けた5月小満の頃、からむし焼きのシーンから始まる。燃え広がる炎と、それを静かに見つめる人々、そして静寂の合間の一節の労働歌は、まるで厳かな儀式のようだ。昭和村では、からむしに携わる人たちは、「からむしの声を聴く」のだという。そこにあるのはきっと、伝統や技能の継承を超えた何か、なのだろう。
一方、「ブーンミの島」では、繰り返し神事のシーンを映し出す。糸績みや織りをする女性たちが、御嶽(うたき、島の聖域)を司る神女(ツカサやサスと呼ばれる)を勤める例は実際に多く、映画に登場する織手の女性はいう。「糸績みや織りをしていると、見えないものが見えるようになるみたいだ」と。実際、わたしもそんな女性たちから、不思議な話を良く聞いた。見える世界と見えない世界のあわいに身を置くような彼女たちのことを、島では、神高い(カンダカイ)人と呼ぶ。
精神世界に饒舌な宮古島と比べ、昭和村に表立った信仰は希薄だ。「からむしのこえ」のパンフレットに、撮影とサウンドを担当した春日聡氏(ブーンミの島では監督を務めている)は書いている。
(以下引用)
かつては「オミドジョウ」(織り終わりの布の端)を祠や観音堂等に奉納し、無事織り終わったことを神仏に感謝するならわしがあった。現在でもみられるが、稀な行為だという。
(中略)
からむし生産にかかわる人びとにとっては、カミもホトケもなく、手のなかのからむしと一心不乱に対峙し、「今年の分」として完成させ、出荷する。そのことだけに集中している。身の丈に合った暮らしのための生産活動は、それ自体が祈りにも似て、尊い。
(引用終わり)
春日氏が記す通り、からむしを授かりもののように扱い、「からむしだけはなくすなよ」と伝え続ける昭和村の人々の営みは、宮古島の祈りと重なって見える。
夏の着物の最上級品として並び称される「西の宮古、東の越後」。ともに国の重要無形文化財に指定されているが、そもそも宮古上布の糸の細さ、軽さ、厳密な精巧さは、島の過酷な歴史が生んだといえる。薩摩の琉球侵攻は、離島に厳しい人頭税をもたらした。サンゴ礁が隆起してできた宮古島の土では、育つ作物も限られる。おまけに島には山も川もない。つまり水がない。そこで女たちに課せられた税が上布だった。織女たちは大変な苦労をして布を織り、その結果、技は極まった。そして人頭税が撤廃されると、宮古上布は島の一大産業となった。その隆盛ぶりは、娘が三人、機を織れば家が建つといわれたほどだ。
越後上布や小千谷縮の原材料となるのが、昭和村のからむしだ。江戸時代から、越後の商人が質のよいからむしを求めて昭和村にやってきた。からむしは貴重な収入源で、村の暮らしを支えたと聞く。凶作で、近隣の村々が多くの死者を出したとしても、昭和村にはからむしがあることで、助かった命があったにちがいない。
ブーもからむしも、自然や為政の脅威に翻弄される人々の傍らにあり、その暮らしと命を支えてきた。「からむしだけはなくすなよ」は、宮古島の祈りの言葉と同義なのだと思えてならない。
【宮古のブーがキラになった】
質のよい原麻には輝くような綺羅(キラ)があって、高い値で売れる。昭和村の原麻が洗練され、美しく整えられている一方、宮古島のそれは、いかにも素朴だ。


その差は、夏、年に一度だけ収穫される昭和村のからむしと、年間を通して六回、七回と収穫できる宮古島のブーの、種類や性質が違うせいなのだろうと思っていた。ところが、上映会の翌日に開催されたワークショップで、ブーが見事なキラに変身するのを見たのである。
からむしもブーも、芯を除いた表皮から繊維を取る作業は同じで、宮古島では、ミミガイという小さなアワビの殻を使い、昭和村では、「苧引き盤」「苧引き板」「苧引きご」を使って、繊維部分だけを取り出す。昭和村の道具は、からむしを引くために造られた専用のもので、表皮の細かな不純物までを取り除くことができる。村の人が、その道具で、宮古島から運んできたブーを引いた。すると、ミミガイでは到底取り切れない表皮がすっかり剥がれ、驚くことに、ブーから真っ白で透き通るようなキラが生まれたのだ。
ワークショップでは、ブーンミ(糸を績む)体験もおこなわれていた。昭和村のベテランが、ブーの束を綾とりのように指にかけ、さくさくと績んでいく。そのスピードに驚きながら、宮古島の績み手が、ブーを細く細く裂き、黒い布の上に一本一本並べている。ある程度並べたら、一本、また一本と績んでいく。黒い布を敷くのは、糸が見えるように。それほどその糸は細い。


それを見ていて気づく。ブーとしての価値は、髪の毛ほどの細さに績んだ糸。であれば、キラが生まれるほどに磨いてしまっては、歩留まりが悪いともいえる。藍絣が王道の宮古上布にとって、糸の白さもさほど重要ではないかもしれない。
映画にも出演した宮古島の女性たちは、キラになったブーを見て感激したけれど、だからといって、これまでのやり方を変えることは決してないだろう。そして昭和村のからむしの糸が細く細く績まれることも、きっとない。ただ、たとえば宮古の彼女たちが、昭和村のからむしでブーンミしたら、どんな糸ができ、布が織られるのだろう。もっといえば、その布をあるいは雪ざらしに、あるいは砧うちで仕上げたら、どんな世界が見えるのだろうと、わたしの妄想は止まらない。一度でいい。からむしとブーのそんなハイブリッドな交叉を、いつか見てみたいものである。

