菅家 博昭(かんけひろあき)
昭和7年(1932)生まれの父・清一(せいいち)は、大岐では「いちあんにゃ」と呼ばれている。91歳になっても、「あんにゃ(兄者)」である。対して女性には「あね(姉)」を呼称に付ける。これが敬語、尊称である。
小さな集落内の男女・年齢階層も家(イエ)も血統も違う人々の融和の秘訣について、父は、「兄弟姉妹のように、つきあうことだ」と言う。そのことが、尊称である「あんにゃ」「あね」という言葉に象徴されている。一方、目下(年齢が同級から下)は、呼び捨てである。尊称を付けない。
大岐の集落を離れて、昭和村、そして奥会津全域を見渡しても、この「あんにゃ」(地域によっては「あんつぁ」)「あね」という尊称は有効であると思う。
はじめて出会った古老に聞き書きをするとき、氏名と生年(生まれ育った社会環境を知る)をうかがったあと、「〇〇あんにゃ」という尊称で呼びかけると、話者と私の距離がぐっと近づくのを感じる。
敗戦前後の昭和20年初頭、昭和村では、食糧難という非常事態から「焼畑」が盛んに行われた。逆にいえば、通常農耕として焼畑を行うことなく、換金作物の繊維植物栽培・生産(アサやカラムシ)で暮らしが成り立ち、戦時中戦後の食料が不足し購入できない時代に、緊急避難として焼畑が行われている。この焼畑については、会津生まれの地理学者・山口弥一郎氏が戦前に行った研究に詳述されている。それは戦争がはじまり食糧増産を焼畑で行うことが奨励されたことにもよる。
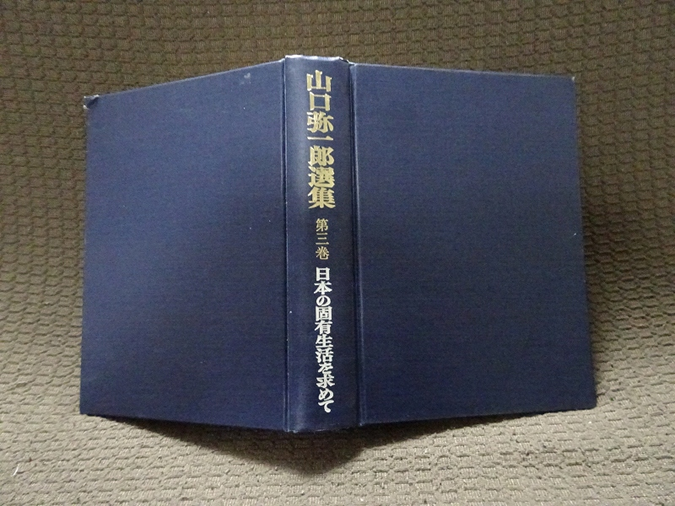
こうした非常事態にも、村人は兄弟姉妹のように力を合わせて非常時を生き抜いてきた。
父・清一が、自力でカノ焼きをしたのは、村の男達が戦場に取られた昭和18年(1943)ころで、ガダルカナル島での玉砕翌年のころである。
年齢は10歳。小学5、6年生の頃だったという。大岐の同級生ら2人とでやったといい、それは村の上(カミ)の2軒目のカズエ、3軒目のサヨと、自分・セイイチだという。子ども3人でカノを経営した、というのだ。
大岐の上流、500mほどに新田と呼ぶ場所があり、その水田に面した斜面を焼いたという。規模は小規模のようだが、7月のはじめに草や灌木を刈取、乾燥させた後に火を付け、翌日にソバを蒔いた。そして2年目はモチアワ、アズキを蒔いたという。その場所の主たる斜面は「青年のカノ」で、大岐の若い人たちが共同でカノを焼いたという。大岐ではタツノ姉(今はスギが植わっている)、作爺(サクジイ)がそこで「カノ刈った」という。分家に出て田畑がとても少ない人たちが焼畑をして食を凌いでいる。
サクジイのカノについては稿を改める。
焼畑は「カノ kano」と会津では呼ぶが、「カノ苅(かり)」「カノ焼き」とも言う。主たる作物は1年目が蕎麦(ソバ)、2年目が粟(アワ)や小豆(アズキ)である。なぜそうした作物かと父・清一に聞くと「ケモノ(獣)が喰わないからだ」という。
山中に拓く焼畑は、獣害が日常である。数年前から、我が家の畑にイノシシが入って荒らすようになった。それは2011年3月の大震災、東京電力の原子力発電所爆発後、撒き散らした放射能物質により、福島県の太平洋沿岸から阿武隈高地の都市・村落が全村避難となり、イノシシ等が人間不在の村落内で増加し、会津地方にも押し出されてきたためである。それまで積雪地の会津にはイノシシは生息していなかった(江戸時代には生息した)。加えてイノシシは土を食べるため、放射能汚染により、13年経過した現在でもイノシシ肉(クマ肉、シカ肉、キノコ類も)は摂食禁止になっている。それは福島県庁のホームページ(インターネットのウェブサイト)で公開されている。
奥会津に残された書面のなかで、1685年の「貞享2年 会津郡伊南古町組 書上帳」(庄司吉之助編『会津風土記・風俗帳 巻2』歴史春秋社、1979年)には焼畑について以下のように記載されている。
鹿野(かの)畑之事
夏土用より始める。山々沢々に焼畑を行う。木草を苅(かり)、土用末これを焼いて蕎麦を蒔く。遅く苅った時は菜(な)を蒔く。また土用過ぎ秋に苅った場合は秋鹿野といい、草は翌年の春まで置いて焼いて粟(あわ)を蒔く。これを「かの畑」「やき畑」という。2,3年ほど作り地方(地力のこと)悪くなると捨て、他所をまた苅り焼く。
大人たちの焼畑の作業を見たり手伝ったりしていたのだろうが、10歳の子どもたちで焼畑を行うほどに、食は逼迫していたのだろう。
2023年8月のはじめ、90歳の父・清一は、新型感染症に罹患し自宅療養となった。そして11月に内臓疾患で会津若松の病院に入院しステント(管)の挿入手術、その後、突発性難聴となり通院、ようやく年を越した。正月22日には内臓痛で、地元の小中津川にある村営の診療所にてレントゲン、血液検査をして説明を受けた。特に左耳が聞こえなくなり私か誰か親族が診察と結果の説明には必ず立ち会う。
高齢者の多い過疎の集落では、かつてのように隣近所で力を合わせて助け合うことがままならない状況となっている。村を出た子どもも高齢の親も、お互い不安を抱えながら、必要に応じて可能な限り行き来しなければ、大切な家族の命を守ることはできない。
子どもたちが銃後を護り、食を繋いできたように、安心できる新たな社会の構成は喫緊の課題である。

